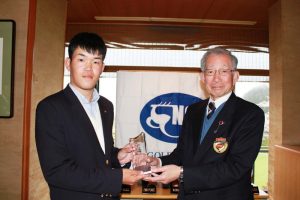1月23日の読売新聞のコラム今日のノートに「17団体の将来」と題して日本のゴルフ界の諸団体の多さに鈴木大地スポーツ庁長官が「これだけ団体があるとどこに何をお話ししていいのかわかりにくい」と皮肉交じりに業界17団体の新年会の講演で切り出したそうだ。
ゴルフ業界に17団体もあったのかと、業界人である私もこの記事を読んで驚きました。早速17団体を調べてみました。
公益財団・日本ゴルフ協会、公益財団・ゴルフ緑化促進会、一般社団法人・日本ゴルフ場経営者協会、公益財団法人・日本パブリックゴルフ協会、社団法人・全日本ゴルフ練習場連盟、一般社団法人・日本ゴルフ用品協会、一般社団法人・日本ゴルフトーナメント振興協会、公益社団法人・日本プロゴルフ協会、一般社団法人・日本ゴルフツアー機構、一般社団法人・日本女子プロゴルフ協会、日本ゴルフ関連団体協議会、NPO法人・日本芝草研究開発機構、全国ゴルフ会員権取引業団体連絡会、全国ゴルフ場関連事業協会、日本ゴルフコース設計者協会、日本ゴルフジャーナリスト協会、日本ゴルフ場支配人会連合会と確かにゴルフ業界には17団体が存在してました。
これらの団体の活動といえば
①日本ゴルフ協会:1924年(大正13年) に創設。日本のアマチュアゴルフ界を統括するとともに、世界共通のゴルフ規則の日本語版の制作を通じたルールとエチケット、マナーの普及活動など日本のゴルフ界の総元締めともいわれる存在です。
②ゴルフ緑化促進会:会員ゴルフ場の協力を得て広くゴルファーから募っている「緑化協力金」(1人1日50円)を主な活動財源に、創設以来全国約8,500ヵ所、195万本以上の植樹を行うなどの活動をしている。
③日本ゴルフ場経営者協会:会員制ゴルフ場経営者団体として1969年(昭和44年)に設立、通商産業省(現・経済産業省)より社団法人認可を受ける。ゴルフ場事業者へのさまざまな指導や勧告、寄せられる相談の処理、ゴルフ会員権預託金償還や税金の問題などゴルフ業界全般の諸問題についてもいろいろな角度から研究・分析を行っている。
④日本パブリックゴルフ協会:生涯スポーツと言われるゴルフの普及振興を事業目的に掲げ、国民の健康の保持増進、余暇活動の充実等、豊かな国民生活の実現への寄与を目的として組織された。
⑤全日本ゴルフ練習場連盟:ゴルフ練習場経営者の全国組織(練習場数:約500場)として1952年(昭和27年)に発足しジュニアゴルファーの自己啓発や社会性を育む「ジュニアゴルファー検定制度」を展開。青少年へのゴルフの普及・育成及び一般ゴルファーの底辺拡大に取り組んでいる。
⑥日本ゴルフ用品協会:ゴルフ用品産業の健全な発展を目的に発足。
⑦日本ゴルフトーナメント振興協会:国内プロゴルフトーナメントの男女主催者、テレビ局、広告会社、運営会社などさまざまなトーナメント関係企業がトーナメントにおける安全対策、メディア報道の検討、社会貢献活動の提唱、また業界発展に向け男女プロゴルフ団体との協働などを推進している。
⑧日本プロゴルフ協会:日本の男子プロゴルファーを統括する組織。プロゴルファー認定の団体としてプロテストを実施するとともに、ゴルフの普及・発展に向けた指導者(ティーチングプロ)の育成を行っている。
⑨日本ゴルフツアー機構:我が国における男子ゴルフツアートーナメント事業を統括する団体。
⑩日本女子プロゴルフ協会:女子ツアーの活性化をはかるとともに女子プロゴルファーの資質向上、ゴルフの底辺拡大・普及を図っている。
⑪日本ゴルフ関連団体協議会:日本ゴルフ協会、日本ゴルフ場事業協会、ゴルファーの緑化促進協力会、日本パブリックゴルフ場事業協会、日本ゴルフ用品協会の公益法人5団体により1991年(平成3年)に設立。ゴルフ場利用税撤廃運動や国家公務員倫理規程の見直し(条文からゴルフの3文字削除)、ゴルフ場用地の固定資産税の適正評価、ゴルフの学校体育正科化など、ゴルフ業界窓口として関係省庁等への陳情活動を積極的に行っている。また、日本ゴルフサミット会議の運営事務局を努め団体間の連絡・情報交換等をサポートする。
以下の諸団体は組織名からその目的はは理解できると思われるので割愛しますが、いずれにしても17団体がまとまってゴルフ人口の減少を食い止め、17団体の新年会スローガンである「ゴルフはみんなのスポーツへ」一丸となって取組むことが必要だと思います。
奈良柳生カントリークラブ 総支配人・阪口 勇