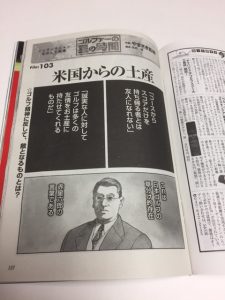日本ゴルフ協会(JGA)税務対策等部会・小宮山義孝部会長名でゴルフ場利用税に関する自民党税制調査会小委員会の結果についてFAXが本日届きましたので全文ご紹介します。
12月6日(水曜13時~17時)、自民党税制調査会小委員会(通称○×打ち出し)が開催され、各省庁の平成30年度税制改正要望の審議が行われた。
会議では赤池誠章(参/比例全国)文部科学部会長をはじめ7名の議員が「ゴルフ場利用税廃止」の発言を行い、原田憲治(衆/大阪9区)総務部会長他2名の「ゴルフ場利用税堅持」の発言を圧倒しましたが、文部科学省(スポーツ庁)の税制改正要望「ゴルフ場利用税廃止」については、昨年同様「二重△」の結論となり、平成30年度の廃止実現はならず、継続検討事項となりました。
「利用税堅持派」議員の発言は、「市町村の貴重な財源」「市町村長が反対しているから」というものであり、課税根拠を失っていることを自ら証明しているものでした。
これに対し、スポーツ庁が提示したゴルフ場利用税が廃止された際の代替財源案に対し総務省側が聞く耳を持たない姿勢に、ゴルフ場と市町村がWinーWinの関係が築けるように総務省とスポーツ庁で協議の場を設け検討していくべき等の意見が出されました。また、城内実(衆/静岡7区)経済産業部会長から、「経産部会長として、今回の税制改正要望を支持する。ゴルフは貴重な産業。地方と良く話し合って良い方向性を見いだすべき」との応援発言も出されました。
2020年東京オリンピック・パラリンピックまでにゴルフ場利用税廃止実現ために残された時間は、来年の税調までの1年間となります。ご支援いただいている先生方及びスポーツ庁のご指導のもと全力を尽くしてまいりますので、引き続きご支援、ご協力賜りますようお願い申し上げます。