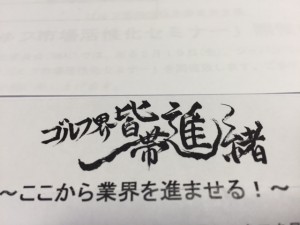広大な敷地に18ホールがレイアウトされたゴルフ場ですが、どこからボールが飛んでくるか分かりません。早い話、いつ危険が襲ってくるか分かりません。隣りホールからボールが飛んできたり、あってはならないことですが後方からボールが飛んでくることもあります。打った本人はまず大きな声で「フォアー」と叫んでください。
隣や後ろから「フォアー」という声が聞こえたら、まずボールが飛んでくるかもしれないと両手で頭を覆い体を小さくして防御体勢をとるようにしてください。
後続組のプレーヤーが前の組に届きそうな距離の所から絶対に打ってはいけないのはゴルファーとしての常識であり当然の心得です。しかしながら正確にショットするプロやシングルゴルファーなら自分の飛距離を十分に把握しているので、前の組が飛距離外に出るまで待てますが、初心者やヘボゴルファーだと200ヤード以上あれば滅多にナイスショットはしないだろうと打ってしまいがちです。
このレベルのゴルファーだとミスショット9に対してナイスショット1の確率だから、待ちチョロが嫌でついつい待ちきれずに打ってしまうことがあります。得てしてこういう場合に10分の1の確率のナイスショットが出て打ち込んでしまうことになります。
もし打ち込みをした場合の謝罪は、即刻前の組に帽子をとり大きな声で謝るととともに、駆け足で前組のプレーヤーの元に行き、あらためてお詫びすることが必要です。大事なのは打ち込んだ時に帽子をとり謝り、許しを請うたので、それで終わったと思うのは間違いです。
次のティインググランドやコース売店やレストラン、ロッカー室などで前の組に追いついた時に正対して「〇番ホールで打ち込んでしまい申し訳ありませんでした」ときちんと謝罪をし許しを請うことが大事なのです。
奈良柳生カントリークラブ 総支配人・阪口 勇